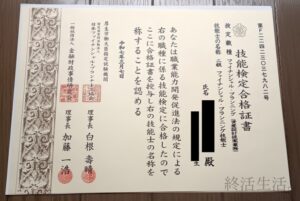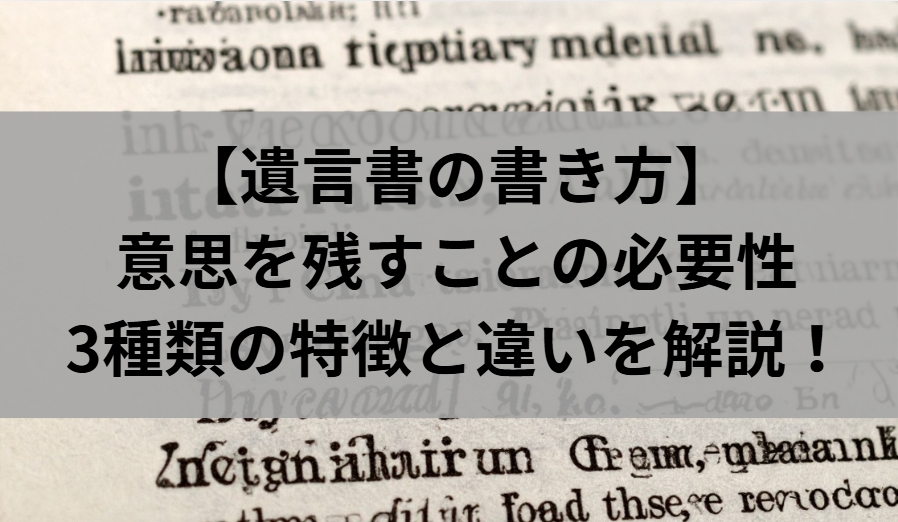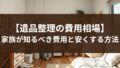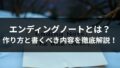遺言書の必要性と種類、ケース別の書き方を解説します。遺言書を残すことの必要性が理解でき、自分に合った種類が選べるようになります。
遺言書がないと、残された大切な人へ自分の意思が正確に伝わりません。
遺言書は、亡くなった後に自分の意思を伝えるための法的な効力を持つ書類です。残された人の相続トラブルを防ぐためにもしっかり理解しましょう。
※当コンテンツは、「記事制作ポリシー」に基づき作成しています。事実と異なる誤認情報がみつかりましたら「お問い合わせ」までご連絡ください。
遺言書とは
遺言書とは、生前に自分の財産をどのように分けるかを決めておく大切な文書です。亡くなった後、残された財産をどう配分するかについて、自分の意思を残せます。
遺言書が必要な理由
遺言書は、自分の意思を法的に確実に伝えるために欠かせません。法律で相続分は決められていますが、望みと一致するとは限りません。
作成することで自由な分配を指定でき、相続トラブルや家族の争いを防げます。遺産を円滑に整理する有効な手段といえるでしょう。
さらに寄付の指定や非親族への継承、保険や年金の取り扱い、ペットの世話など細かな希望も残せます。遺言書は安心につながる大切な備えです。
遺言書の種類
遺言書には下記の種類があります。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成する方式で、証人は不要です。全文を自筆し、日付・署名・押印を備えることが求められます。
他人を介さず意思を伝えられる利点がありますが、紛失や破棄の恐れがあるため保管方法には注意が必要です。書式を守らなければ無効となる点も理解しておくべきでしょう。
法務局に預けなければ、遺言者の死後に家庭裁判所で検認手続きが必要になります。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言で、内容が正確に反映され法的効力も高まります。公証人役場で保管されるため紛失の心配が少なく、信頼性に優れています。
作成には2人以上の証人が必要で、他の形式より費用はかかりますが、相続手続きがスムーズに進み、偽造や改ざんのリスクもほとんどありません。
未成年者や言語障害がある人も、公証人の支援を受けて作成できます。ただし遺言者の死後に自動通知はされないため、遺言の存在を相続人へ伝えておくことが重要です。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を第三者に知られず残したい人に適した方法です。遺言者が自ら作成するか代筆し、二人の証人立会いのもと封筒に収めて署名・押印します。
証人は封筒が遺言書であることを確認するだけで、内容は開示されません。そのため意思を守れる一方、誤記や不備で無効になる場合や、紛失リスクに注意が必要です。
遺言者の死後は、家庭裁判所で検認手続きを行い、正当性を確認します。要件を理解し、確実に意思を伝える工夫が求められます。
ケース別の遺言書の書き方
遺言書の書き方を以下のケースごとに解説します。
1.妻に全ての財産を相続させたい
妻に全ての財産を相続させたいと考える場合、自筆証書遺言が一般的です。妻を唯一の相続人として遺言書に明記することで、自分が亡くなった後の財産を明確にできます。
遺言書は全文を自筆で記述し、日付と署名、押印を行います。財産の詳細と妻に相続させることを明記してください。記載内容には、妻の氏名と生年月日も必要です。
正しい手順で遺言書を作成し、適切に保管することは残された家族への思いやりとしても機能します。
2.親にも財産を分けたい
親にも財産を分けたい場合、遺言書を用いて意向を明確に示すことが重要です。遺言書には財産の分配を明確に指定し、理由も記載することをおすすめします。
遺言書を作成することで、遺産分割に関する誤解や親族間のトラブルを未然に防げます。親への財産の分配を考える際は、相続税の影響も念頭に置くべきです。相続税に関しては専門家と相談することが役立ちます。
遺言書はいずれの種類でも、親への財産分けの意向を正確に反映させることが可能です。
3.特定の団体に財産を寄付したい
特定の団体に財産を寄付したい場合、正式名称や寄付する財産の詳細な内容を記載する必要があります。寄付した財産が特定の目的や条件で使用されることを望む場合は、用途や条件を詳細に指定しましょう。
遺言書を無効にしないための注意点
遺言書を作成する際には、無効になるリスクを減らす必要があります。
遺言書が正しく効力を持つために注意すべきポイントは以下のとおりです。
1.遺言書が無効になるケースを把握する
不適切な形式や不備のある遺言書は法的効力を持ちません。遺言書が無効になると、遺族間で争いが生じたり、遺言者の最後の意思が反映されなかったりするため、注意しましょう。
遺言書が無効になる具体的なケースは以下のとおりです。
- 法定の形式に従わない
- 遺言能力が欠如している
- 強制・脅迫により作成された
- 偽造または変造された
- 証人の形式要件に不備がある
- 遺言書が発見されず確認できない
遺言書には法律上の形式が定められており、これに従わなければ効力はありません。遺言者が認知症などにより意思を理解できず合理的な判断が困難な場合は、遺言能力がないとされます。
また、強制や脅迫によって作成された遺言書は無効です。他人による偽造や内容の改ざんがあった場合も当然認められません。
さらに、証人が法的要件を満たしていなかったり、遺言書自体が発見されない場合も効力を失います。正しい形式と保管が有効な遺言書の前提条件です。
2.明確な内容を記載する
遺言書には、誰が何を受け取るのかを明確に記載することが重要です。遺言書の内容が不明確な場合、解釈が分かれ、相続人間で争いが生じる可能性があります。
財産の分配方法や相続人ごとの分配割合などを詳細に記載しましょう。全ての財産と具体的な内容を記載し、それぞれの財産を誰に譲るのか、しっかり明示します。法律用語を正確に使用し、誤解や曖昧さを避ける工夫も大切です。
3.内容の変更は正しい方法で行う
遺言書の内容を変更する際には、正しい方法を用いる必要があります。具体的な手順は以下のとおりです。
- 訂正箇所を二重線で訂正
- 訂正箇所に「ここを訂正します」と明記
- 訂正箇所に署名押印
- 訂正箇所を一覧にして明示
適切な方法で訂正すれば、訂正後の内容が明瞭であることが保証され、遺言書の信頼性が保たれます。大幅に内容を変更する場合は、古い遺言書を廃棄し、新しい遺言書を作成しましょう。
4.遺留分の侵害を避ける
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる相続財産の割合を指します。遺言書を作成する際は、この遺留分を侵害しない内容にすることが重要です。
具体的に相続分を明記すれば、遺留分を守った分配が可能になります。専門家に相談して計算や配分を確認することで、適切な遺言内容を整えられるでしょう。
遺留分を考慮した遺言書を残すことで、相続トラブルを未然に防ぎ、家族の負担を軽減できます。
遺言書作成を専門家に依頼するメリット・デメリット
専門家に依頼するかどうかを決める際には、メリットとデメリットを比較してよく検討しましょう。
メリット:遺言書が無効になりにくい
専門家が遺言書の作成をサポートすると、無効になるリスクを大きく減らせます。法律に準拠した形式と内容で作成できるため、不備や誤りが少なく、有効性を確保できる点もメリットです。
遺留分の侵害や他の法律問題を回避しやすくなり、将来の紛争を防ぐためのアドバイスを受けることも可能です。最新の法律に基づいた内容で遺言書を作成できる点でも、安心感があります。
デメリット:費用がかかる
弁護士や司法書士に遺言書作成を依頼すると、相談料や書面作成費として数万円から十数万円ほど必要になります。公正証書遺言の場合は公証人手数料も同程度かかり、遺言執行者を任命すれば遺産規模に応じた報酬も発生します。
さらに、面談や相談には交通費や時間的負担も伴います。専門家を選ぶ際に時間や労力がかかる点もデメリットといえるでしょう。
遺言書の作成に関するよくある質問
実際に遺言書を作成する際に疑問を感じやすい以下の点について解説します。
1.遺言書に財産目録を添付する方法は?
遺言書の内容をより明確にするために、財産目録を添付しましょう。財産目録とは、遺言者が所有する財産の種類と詳細を一覧にしたものです。遺産の詳細が明確になり、相続人間のトラブル防止に役立ちます。
財産の種類別に財産目録に記載すべき内容は、以下のとおりです。
- 不動産:土地や建物の所在地や登記情報
- 預貯金:銀行名、支店名、口座番号
- 有価証券:証券会社名、銘柄、数量
財産目録には作成年月日を記載し、署名押印します。財産目録は遺言書の一部として効力を持つため、正確かつ詳細に作成することが重要です。
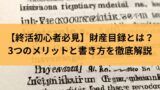
2.遺言書はパソコンで打ってもいいの?
遺言書の種類によって求められる作成方法が異なります。ルールに従って作成しないと、遺言書として認められないため注意しましょう。
遺言書の種類は以下の3つです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言の場合、日付や署名を含む全文を自筆で書く必要があります。2020年の法改正で、財産目録のみパソコンでの作成が可能となりました。公正証書遺言と秘密証書遺言は、形式や内容が適切かを公証人が保証するため、パソコンでの作成が可能です。
団体の担当者が決まっている場合は、連絡先や担当者の名前も遺言書に記入してください。遺言書を書くことで寄付に関する意思が遺族や関係者に伝わり、意向に沿った形で進められます。
遺言書の書き方のよくある質問
遺言書の書き方でよくある以下の質問を解説します。
1.遺言書に署名代行はできる?
遺言書には遺言者本人の署名が必須で、原則として代筆は認められません。体調が悪く筆跡が乱れても、自ら署名したものであれば有効です。
例外は公正証書遺言で、公証人や証人の立会いのもと口頭で意思を伝え、公証人が文書にする仕組みです。署名や押印ができない場合でも、公証人が記録し証人が確認すれば有効となります。
代筆は法律で厳しく制限され、病気などで自書が不可能な場合のみ特例として認められます。
2.遺言書の保管方法は?
遺言書の保管は有効性を守るために欠かせません。紛失すれば効力を失うため、慎重な取り扱いが必要です。
自宅の金庫で秘匿性を保てますが、盗難や火災のリスクがあります。自筆証書遺言は法務局の保管制度、公正証書遺言は公証人役場で預けられるため、より安全です。
また、弁護士や公証人といった専門家に預ける方法もあります。定期的に保管状況を確認することが、紛失防止につながります。
3.遺言書はいつから効力がある?
遺言書は、遺言者が亡くなった時点で初めて効力を持ちます。生前は意思を示す文書にすぎず、法的効力はありません。
死後は遺言内容に従って遺産分割が行われ、死亡を証明する書類とともに保管されます。ただし効力を発揮するには、要件を満たした遺言書が存在していることが不可欠です。
4.複数の遺言書が見つかった場合はどうなる?
複数の遺言書が見つかった場合は、最新の日付のものが優先されます。内容が矛盾していても、後の日付で作成された遺言が有効と判断されるのが原則です。
ただし、全ての遺言書を確認し矛盾点を検討する必要があります。相反する内容がある場合は裁判所の解釈に委ねられることもあり、専門家の助言を受けながら手続きを進めることが安心につながります。
まとめ
遺言書は、自分の財産についての意思を残すために大切な書類です。遺言書を残すことで相続トラブルを避け、大切な人に対して財産の分配を明確に伝えられます。
遺言書には、以下の3種類が存在します。
- 自筆証書遺言:遺言者が自筆で全文を書く方法
- 公正証書遺言:コストはかかるが、信頼性の高い方法
- 秘密証書遺言:内容を第三者に知られない方法
特定の家族や団体に財産を残すには、遺言書が重要な手段となります。作成には本人の署名が必要で、保管方法も紛失リスクを考えて選ばなければなりません。
遺言書は遺言者の死後に効力を持ち、複数ある場合は新しい日付のものが優先されます。適切に作成・保管することで、自分の意思を正確に伝えられるでしょう。
参考サイト
- 環境省
- 国土交通省
- 経済産業省
- 日本介護協会(一般社団法人)
- 日本在宅介護協会
- 公益社団法人 全国有料老人ホーム協会
- 高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)
- 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
- 全日本葬祭業協同組合連合会(全葬連)
- 全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)
- 全日本冠婚葬祭互助支援協会(全冠協)
- 全国儀式サービス
- 一般社団法人 遺品整理士認定協会
- 一般社団法人 日本遺品整理協会
- 一般社団法人 生命保険協会
- 日本損害保険協会
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
記事監修&著者プロフィール
 名前:バッハ・杉山
名前:バッハ・杉山
ファイナンシャルプランナー(2級)
現場歴28年。